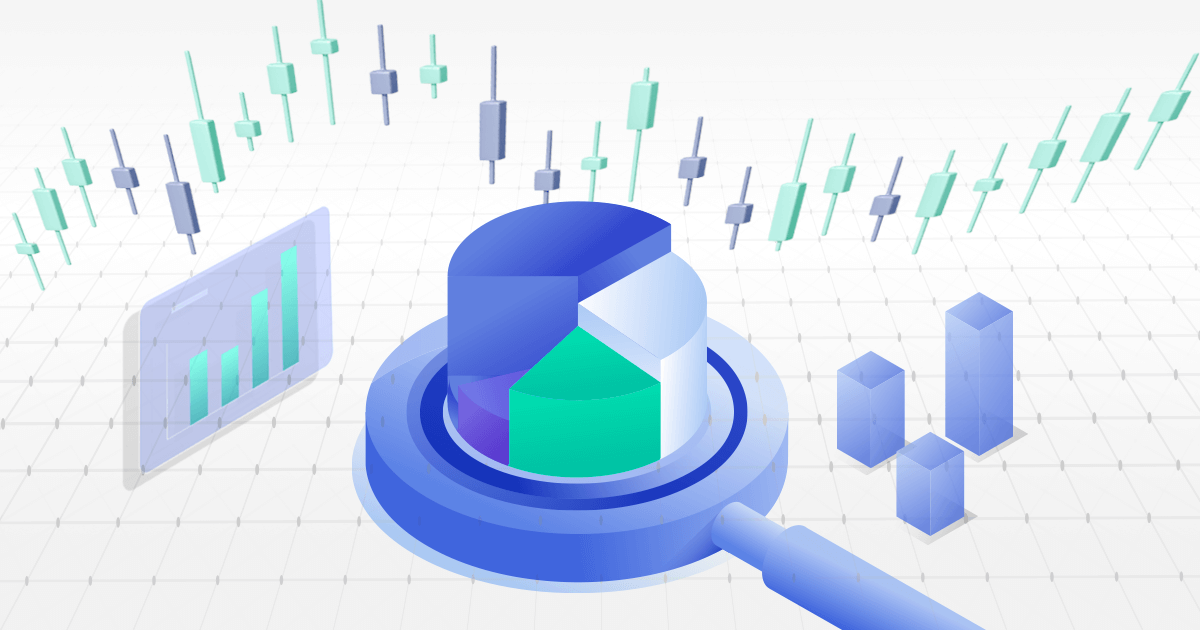内部留保


内部留保
内部留保とは、事業を通じて生み出した利益から、税金・配当・役員報酬など社外に流出する分を差し引いた残りのお金で社内に蓄積されるものをいいます。利益は損益(フロー)ですが、内部留保は資産(ストック)です。
内部留保という項目は決算報告書のどこを見ても記載はなく、一般的な概念です。通常は貸借対照表に記載される「利益剰余金」を指して内部留保と呼ぶことが多いです。総資産に対する内部留保の比率は、財務の健全性を示す指標として注目されます。
利益をどのように分配するかは、企業の経営方針や財務の状況などに左右され、決まったルールや手法はありません。株価上昇を目標に株主還元を重視するなら、配当や自社株買いにあてられることが多くなります。一方、財務基盤を強化するなら負債の返済や、内部留保を増やすこととなります。日本企業は欧米に比べて内部留保の割合が多く、資産が多い割に収益性や効率性に欠けるといわれてきました。これが問題視され、近年では株主重視政策や買収防衛策として、内部留保を取り崩して配当に回す企業が増えています。
内部は、使わずにため込まれた現金であるとのイメージが強いですが、内部留保は現金であるとは限りません。貸借対照表に記載されている利益剰余金は、毎年の「利益の残りが積み上がったもの」という意味でしかなく、それが現金なのか、投資されて生産設備などに置き換わっているのかは分かりません。本来投資に回ることもあるお金ですが、近年は現預金で保有される金額が多くなり、景気回復を阻害していると批判されていました。2020年に発生した新型コロナウイルスにより、現預金で保有していた内部留保が資金繰り悪化を防ぐのに役に立ったことから、今後も現預金で保有するケースが多くなるのではないかと懸念されています。
作成日
:
2021.05.14
最終更新
:
2024.11.19
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。